生活習慣改善講話
最終更新日 [2023年10月2日]
10月に入りました。令和5年度も半分が過ぎたことになります。気候も涼しい風を感じるようになり、過ごしやすい時期となってきています。様々な活動を通して学校・学年・学級を練り上げる「練り上げの2学期」の大切な1か月となります。各ご家庭でも励ましのお声がけをお願いいたします。
ところで、先週は、様々な方法でご案内をしました「生活習慣改善講習会(講師はサンクスの杉野伸治先生)」を28日(木)に実施しましたので、以下、その内容の一部を紹介します。
【脳の働き】
コミュニケーション・行動のコントロール・やる気・記憶・集中・注意・我慢・思考力・感情のコントロールなど(非認知能力)のストレスを抑える力は脳の前頭前野の働きであり、25歳で完成する。
ストレスを生み出すのは脳の偏桃体の働きであり、17歳で完成する。
【脳の発達に危険なこと】
ゲームやスマホの使い過ぎは脳の前頭前野の発達を阻害するため、ストレスに弱い人格になっていく。1時間以上の使用は記憶力の低下に、特に、3時間以上の使用は人格形成に影響が出てくる。勉強しても、ゲーム・スマホを長時間使うと勉強内容が身につかない。
「インターネットパラドックス」という言葉ある。ネット上での人とのつながりは現実社会でのコミュニケーション能力の低下や友人の減少につながり、孤独感が増大する。
ゲームやスマホは1時間以内に抑えておくことが大事だが、ゲームやスマホは快感物質(ドーパミン)を発生させるため依存性が高く、発達の途上にある中学生にはそのコントロールはできない。大人の介入が必要である。
偏食(食べ物の好き嫌い)が多い人は、人の好き嫌いも多い。それがストレスにつながる。
やらなければならないことは知っている。しかし、やろうと思ってもできない。義務を果たせない。それがストレスになる。そして、様々な不適応行動につながる。
【前頭前野を育てる生活習慣を確立しよう!】
睡眠は大事である。中学生段階では8時間45分の睡眠時間が必要で、脳の整理整頓と身体のバランスを整える効果がある。睡眠時間が6時間をきると精神疾患のリスクが高まる。就寝時はゲーム・スマホを身近に置かない。
帰宅後は入浴を早くする。シャワーだけではなく、夏場でも湯船に浸かる。心身をリラックスさせ、早めの就寝につなげる。
テレビを見ながらの食事はしない。家庭内の会話を増やす。そして、好き嫌いをなくす。
「早寝・早起き・朝ごはん」は重要である。特に、「朝ごはん」は午前中の活動を支える大事なものであり、パンよりも米が良い。
日常生活のルーティーン化を図り、長期休業中もそのリズムを崩さない。
言葉の力は大事である。言葉で伝えることができなければ、感情で伝えることになる。感情のコントロールには前頭前野の発達が欠かせないため、言葉を知る取組(特に読書)は重要である。まずは漫画から。そして、小説へ。最終的には自己啓発本へ。
自分の弱さ(できないこと)を受け入れて、親に頼らず自分で物事を処理する範囲を増やしていく。それが自立である。自立することが自由につながる。そして、努力することそのものが自立という結果を生む。
運動は脳の薬。運動は大切である。登下校はできる限り歩くこと。学校までの送迎は避け、歩く時間を増やす。
【まとめ】
過去と自分以外の人は変えられない。自分と自分の未来を変える。そのために生活習慣を変えるトレーニングを行う。いきなり全部を変えるのではなく、少しずつ変えていく。
「支えてもらう喜び」から「できるようになる喜び」へ、そして「支えることのできる喜び」へと変化することが大人に成長することである。
|
|
|
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Reader(R)が必要です。
右の「アドビリーダーダウンロードボタン」をクリックすると、アドビ社のホームページへ移動しますので、お持ちでない方は、手順に従ってダウンロードを行ってください。 |
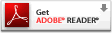
(新しいウィンドウで表示) |
|

